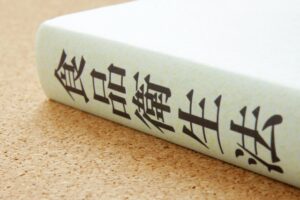食品事故はどんなものがあるのか
食品事故って何だ?
毎日の生活の楽しみでもある、美味しい食べ物。家族で囲む食卓のごはん、スーパーやコンビニで買ったお弁当、友達で楽しむ外食など、色々な場面がありますね。でも、ごくまれに、これらの食品で体調を崩してしまうことがあります。これを「食品事故」と言います。
食品事故には、大きく分けて3つの種類があります。今回は、それぞれの事故がどうして起こるのか、具体例を交えながら解説していきます。
1. 微生物による食品事故
この種類の食品事故は、私たちの目には見えない小さな生き物、つまり細菌やウイルス、寄生虫が原因で起こります。

- 細菌
- 代表的なのは、サルモネラ菌やO157(オーイチゴーナナ)、カンピロバクターなどです。これらは、加熱が不十分な肉や卵、生野菜などについていることがあり、お腹の痛みや下痢、吐き気などの症状を引き起こします。
- たとえば、生の鶏肉を切った包丁やまな板で、そのまま野菜を切ってしまうと、菌が野菜についてしまい、食中毒の原因になることがあります。
- ウイルス
- ノロウイルスなどが有名です。ウイルスは、調理する人の手に付着していたり、汚染された水や食べ物から感染することがあります。
- 特に冬に流行することが多く、強烈な吐き気やおう吐、下痢などの症状が出ます。カキなどの二枚貝が原因となることが多いです。
- 寄生虫
- 魚介類にいるアニサキスが代表的です。アニサキスは、生のサバやイカなどに寄生していて、これを生で食べてしまうと、激しい腹痛を引き起こすことがあります。他にも、ヒラメのクドアも有名です。一昔前だと、サナダムシとか回虫、クリプトスポリジム・・・元寄生虫病学研究室としてはもっと解説したいですがこの辺で。
- そのため、魚や野菜を食べる際は新鮮なものを選んだり、冷凍や加熱、洗浄殺菌をしっかりすることが大切です。
2. 異物による食品事故
食べ物ではないものが、食品の中に混ざってしまう事故です。特に飲食店では度々ニュースになりますね。

- ガラスや金属など(硬質異物)
- プラスチックの破片やガラス、金属片などが挙げられます。これらが混入すると、食べてしまった人が口の中を切ったり、歯が欠けたりする危険性があります。
- たとえば、製造過程で機械の一部が欠けて食品に混ざったり、原材料に虫がついていたりすることがあります。
- 毛髪や糸など(軟質異物)
- 調理する人の髪の毛や、洋服の繊維などが食品に入ってしまうことも異物混入に含まれます。
- 小さなハエやゴキブリなどもあります。そのものの健康被害は小さいかもしれませんが、精神的には大きなダメージとなります。
3. 化学物質による食品事故
化学物質が原因で起こる食品事故です。意図せず食品に混ざってしまったり、誤って使われてしまったりすることがあります。
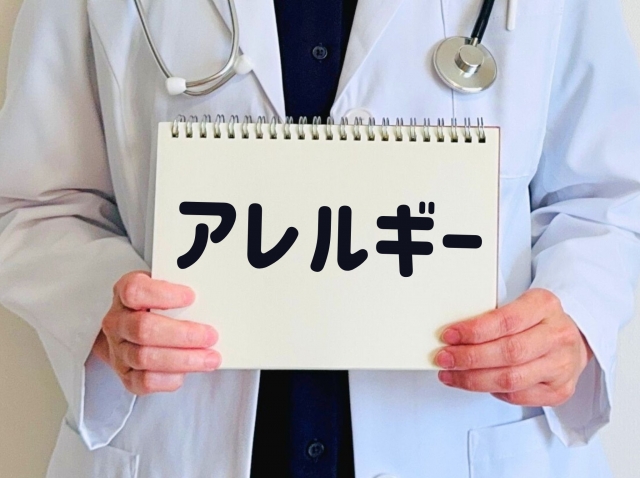
- アレルギー物質(アレルゲン)
- 本来無害である食品に含まれるタンパク質に、免疫機能が間違えて反応して体調不良になることがあります。”そば”や”えび”は有名ですね。アレルギーをお持ちの方は、自分を守るため注意していることが多いのですが、製品の表示ミスや飲食店の店員から間違ったアレルギー情報を聞いて発症するケースもあります。最悪の場合、死に至るケースもあるので、細心の注意が必要です。
- 洗剤や油などの混入、誤提供
- 食品工場や飲食店の機械を洗浄するための洗剤や、機械の潤滑油が、誤って食品に混ざってしまうケースもあります。「いやいや、そんな間違えることはあり得ないでしょ」と思われる方は多いのですが、意外と事故が発生しています。よくあるのが、殺菌用の次亜塩素酸ナトリウム溶液を間違えて飲料水として提供してしまった、というケースです。また、アルコール飲料とソフトドリンクを間違えて提供して救急車で運ばれる、なんて事例も多いです。
- 農薬や添加物
- 野菜や果物を育てる際に使う農薬や、食品を加工する際に使う食品添加物が、決められた量を大きく超えて使われたり、本来の意図とは異なる使い方がされると、健康被害を引き起こす可能性があります。
- ただし、食品衛生法によって、何重にも安全を見込んだ基準が徹底されています。なので、普段の食生活で心配する必要はありません。
- 重金属
- 水や土壌を通して、鉛やヒ素などの重金属が植物や魚に蓄積されることがあります。
- 日本では過去に、海外では今も、このような重金属が原因で健康被害が出た事例があります。
食品事故を起こさないようにするために
色々な食品事故があって、どうやって対策すればいいのか不安になりますね。事故をゼロにすることは不可能ですが、起きる可能性はできる限り小さくする必要があります。ここで重要なのが、”HACCP”の考え方です。
HACCPは以前のコラムで簡単に紹介していますが、今回紹介した分類は、「微生物危害」「物理的危害」「化学的危害」とも言えて、HACCPの”危害要因分析”の要素にあたります。これらの危害をどうやって抑えるかが、HACCPの考え方でした。
弊社では、食品製造に関わる皆様が、このような事故を未然に防ぐためのサポートを行っています。お気軽にお困りごとをご相談ください!